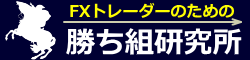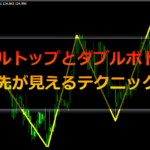今回はプロスペクト理論のお話をしたいと思います。
プロスペクト理論とは、ダニエル・カーネマンとエイモス・ドベルスキーによって考案された意思決定モデルの一つです。
行動経済学の先駆けとして2002年にノーベル経済学賞を受賞した、人間の歪みを理解するための非常に重要な理論です。
こうやって説明すると、ちょっと難しい印象になってしまいますが、プロスペクト理論は誰もが経験したことがあると思います。例を出しながらご紹介します。
プロスペクト理論
損失時の苦痛>利益時の満足
人間は、利益から得られる精神的満足度よりも同額の損失から受ける精神的苦痛の方が大きく感じると言われています。
そして2回目のトレードで10万円負けたとします。
収支としてはプラスマイナス0円です。
しかし、精神的にはプラスマイナスゼロにはならず、苦痛の気持ちの方が勝っている、ということになります。
もう一つ例を出しましょう。
そして2回目のトレードで9万円負けて、3回目のトレードで10万円負けたとします。
収支はプラス1万円です。
トータルではプラスになっているにもかかわらず、3回トレードして1万円勝った!と喜ぶ人よりも、2回目と3回目の損失額の合計である19万円を失って苦痛に感じる人の方が多いのではないでしょうか?
確率論を本当の意味でなかなか理解できない
有名な例ですが、次のような2択が与えられると1を選ぶ人が多くなります。
1:確実に10万円もらえる
2:40%の確率で30万円もらえるが、60%の確率で1円ももらえない
計算してみると、期待値としては2の方が高い(30万円×40%=12万円)ので、2を選択する方が合理的となりますが、人は目先の確実な利益を失うことを避ける傾向にあります。
つまり、人間は合理的な行動を続けることは難しいということですね。
ちなみにこのような行動をとる人を、損失回避人間と呼びます。
極端に損失を出すことを嫌う人のことですね。
損失回避人間がトレードをすると辛い
では損失回避人間がトレードを行うとどうなるでしょうか?
当然ですが、損失をあらゆる手段を使って回避し、その一方で目先の利益を確保するように動くでしょう。
すると、損切りは出来るだけ遅く、利食いを早く行う、という正に損大利小のトレードを繰り返すことになります。
そうです。
初心者トレーダーがやってしまいがちな「損切りは遅く、利食いは早く」というトレードは、プロスペクト理論に支配された行動で、合理的に欠くトレードなのです。
実際に私も損大利小のトレードをしていました。
特に利食いを苦手としており、目標利食い地点に届く前に決済してしまうことが多くありました。
過去チャートから検証を行って、優位性のあるトレード手法だと確信を持っているはずなのですが、利食いを待つことが出来ませんでした。ロングして含み益が出ていて、ちょっとでも下げてくると不安で不安で仕方がなくなって、気づけば決済していました。
損失回避人間からの脱却
この悪癖を解消するにはどうしたらいいか?
色々と考えた結果、とりあえずエントリー注文を入れたらOCOで損切りと利食いを決めてパソコンをシャットダウンしてしまうことから始めました。
すると次は携帯アプリでチャートを見てしまいます。
これは本当にまずいと思い、携帯からFX関連のアプリを全て削除しました。
そうすると、チャートも見れませんし、決済したくてもできません。
何の情報もありませんから、OCOにかかるのを待つだけです。
これを続けました。
ちなみに、パソコンのシャットダウン直後は、気を紛らわすために激しい筋トレをしていました。
そして、利食いを早めなくても徐々に利益は積み重なっていくんだということを心の底から実感して初めて、損大利小のトレード、すなわち損失回避人間から脱出できたと思っています。
トレードをする環境は人によって様々かと思いますが、パソコンでトレードしている方で、損失回避人間から脱出できないという方は是非一度、試してみて下さい。
プロスペクト理論を克服する方法を分かりやすく解説!